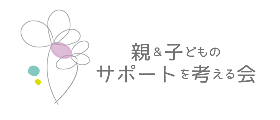なぜ支援が必要か?
誰にも相談できずに
孤立しがちな子どもたち
精神に障がいのある親は、自身の精神状態や症状が、子育てにも影響を及ぼします。このような親と暮らす子どもは、親の示す症状やその対応に悩みながら生活をしていますが、多くは誰にも相談できずにひとりで抱え込んでいます。 しかし、こうした子どもに焦点を当てた支援は、出産後の退院の時期、もしくは子どもに何らかの成長発達の課題が生じた場合に限られ、子どもの生活状況は明らかにされていません。
親も、家事ができない、子どもとのやり取りがうまくできないなど支援を必要としていますが、子どもの養育を奪われることを怖れて、援助を求めない傾向にあります。そのため、これらの親子は、困難・生きづらさが生じても親子で抱え込み、周りの人から孤立するような生活になりがちです。
このような状況にある子どもが、支援を求めやすい環境を作り、健全な成長発達を遂げるよう導くことが必要と考えます。
当会では、社会への啓発活動も必要と考え、『精神障がいを持つ実親と生活する思春期年代の子どもの生活状況の把握と支援に関する研究 (平成21~23年度 科学研究費助成事業(基盤研究・C) 』をテーマに、取り組みで明らかになった子どもの生活状況や思い、支援の必要性を社会に伝えています。
取り組みで
明らかになったこと
知識や情報を得たい
同じ体験者の話を聞き、
繋がりを持ちたい
成人した、精神に障がいのある親と暮らす/暮らした経験のある子どもを対象としたインタビューから明らかになったことは、
病気や障がいの正しい知識が
無いために…
症状を「怠けている」・「性格の問題」と捉えて対応したことで、病状を悪化させてしまったのではないかと自分を責めている。
病気の親に合わせた生活を強いられることで理不尽さを感じている。
病気や障がいのことを
人に言ってはいけないと
言われ続け…
内と外を使い分け、人と距離を置いて接するパターンになってしまう。
精神に障がいのある親の子ども…
精神に障がいのある親から生まれた自分もダメな子どもと、自分も否定されたように感じる。
などでした。そして、これらの子どもは、

知識や情報を得たい

同じ体験をしている
他の人の話を
聞いてみたい、
つながりを持ちたい
と希望していました。
こうした子どもの思いを受け、
同じ体験をしている仲間と集い、語り合う場
として「集い(三重・全国)」の
開催に至りました。
その後の取り組み
「人に言ってはいけない」「家の状況を知られてはいけない」と思っていた子どもたちが「他の人の話を聞いてみたい」、「思いを共有したい」と思えるようになるのは、親や家庭の状況が理解でき、客観的に状況を捉えられるようになる20歳前後ぐらいからと言われています。
そのようになるためには、周りの大人が子どもの存在や状況に気づき、必要な支援に繋げていくことが必要になりますが、 子どもが安心して支援を求めることができるためには、どのような環境(体制)になればよいのか? と考え、『精神障がいの親と暮らす子どもが安心して支援に繋がるための体制作り(平成26~29年度 科学研究費助成事業)』の研究に取り組みました。
精神に障がいのある親と生活する家庭では、障がいにどのように対応するかに悩み、そのことを話題にしないようにしていたりします。多くの子どもたちは障がいの説明を受ける機会がなく、何が起こっているかわからない状況の中で暮らしてきました。そこで、家庭内で障がいのことを自然に話すことができたら‥と考え、現在、“メリデン版訪問家族支援”の技法を用いた介入研究で、親子の関係性や子どもの自尊感情にどのような変化がみられるのかを明らかにする、『精神障がいの親を持つ子どもの自尊心回復に向けたアプローチ -訪問型家族支援の導入-(平成31年~令和6年度 科学研究費助成事業)』の研究に取り組んでいます。
※メリデン版訪問家族支援:支援者が家庭を訪問し、家族も利用者と同じ支援対象と位置づけて家族にまるごとかかわっていきます。障がいや互いの思いを家族で伝えあったり、コミュニケーションスキルを学ぶ(心理教育)プログラムです。